つちのみかた
植物と土壌「保水性があって排水性がよい土地。」
作物の適応土壌を見ると、よくこう書いてあります。
ふかふかで、放線菌の匂いがする黒い土。
なんだか聞くだけでいい土な感じがします。
そもそも、植物は必ずしも土を必要としないのです。
水耕栽培では、土を使わずに育ってますよね。
植物の成長に必要なものは、水と光、そして空気、栄養分。
植物のカラダは、細胞と繊維からできています。
繊維に必要なのは炭水化物。
組成はC(炭素) H(水素) O(酸素)。
光合成を考えてみましょう。
CO2 二酸化炭素 + H2O 水 => C6H12O6 グルコース(炭水化物) + O2 酸素
細胞の活動に必要な窒素(N)、リン酸(P)、カリ(K)
必須ミネラルのマグネシウム(Mg)、カルシウム(Ca)。
そして微量要素と続きますが、いっぱい本が出てるので省略します。
土の役割としては、
植物の体を倒れないように支え、養分や水を供給しています。
土は半径6400kmの地球の表面数メートルにしかありません。
いわば、ほんの表皮にしかすぎないものです。
土は、岩石の風化でできたものです。
太古の歴史を経て、植物や微生物、生き物たちが分解し、有機物を蓄積してきました。
土壌のなりたち
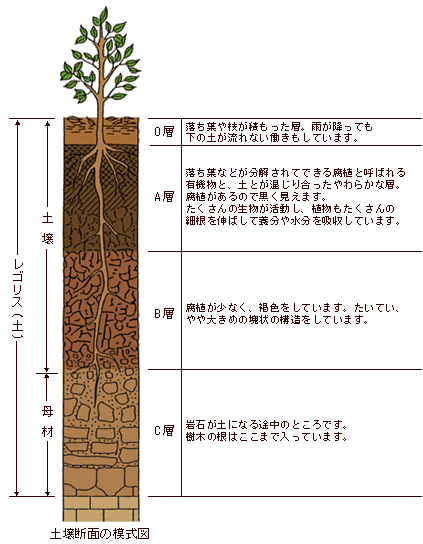 |
| 国立科学博物館より |
それぞれの土壌に適した作物が選択され、地域独特の食生活や文化がなりたってきたのです。
土質が違えば、栽培作物が違う。
いわば、土が文化を作ってきたのだといっても過言ではないでしょう。
人は土をどう認識してきたのか。土の違いによる多様な食文化―。土と民族について研究する学問をエスノペドロジー(民族土壌学)といったりします。
あまり書くと脱線しますが・・・
世界にはどれだけの種類の土壌があるかというと・・・
世界の土壌分布については、Soil Taxonomyとか、Soil Classification(土壌分類)の表がFAO(食糧農業機関)から発行されているので参考にしてください。
FAO soil map
http://www.fao.org/soils-portal/soil-survey/soil-maps-and-databases/en/
日本の土壌分類については、日本ペドロジー学会「土壌調査ハンドブック」を参照
よい土とは?
ふかふかの黒土がいいのかといえば、一概にそうは言えないようです。
日本に多い「黒ボク」は、よさそうに見えますが、リン酸吸収係数が強く、補ってあげないと作物が利用できるリンが少なくなっています。
有機物、腐植が多い土は黒く見えます。有機物が多い土がよいかというと、植物の残渣が堆積した泥炭土(ピート・ソイル)は、pHが低いし、水はけもわるいです。
どういう作物をつくりたいのか、その土は何が不足しているのか、全体を考える必要があります。
一般的に、大きく分けて、
土壌の物理性、化学性、生物性
3つを考慮に入れる必要があります。
土壌診断するにはお金がかかります。
簡易テスト試験器も売られていますが、そんなもの持ってないよ、という方は、とりあえず参考にしてください。
機械に頼ると正確かもしれませんが、どちらかというとアナログな人間なので、料理も計量器を使わずに感覚で作ってしまいます。
オランダの大学で農学生やってたころ、実習でやったのがVisial Soil Assessment(VSA)。
これは、土壌の物理性と生物生をテストするものです。
化学性については正確にはわかりません。
でも、昔の人は、生えている草でpHを判断したり(指標植物といいます)、作物の育ち具合、葉の色、顔色をみて何が足りないか判断していたのです。
まだまだその見地は得られませんが、伝統的知恵に学び、判断できるようになりたいと思います。
さて、visual soil assessmentですが、
断面図や土の色、団粒、斑紋の有無、生き物などを調べて、点数化していくのです。
チェックシートはこちら。
FAO VSA field guide
http://www.fao.org/docrep/010/i0007e/i0007e00.htm
登録:
コメント
(
Atom
)













0 件のコメント :
コメントを投稿